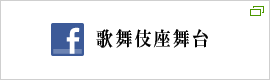歌舞伎座に櫓が揚がりました
11月1日の初日を前に、歌舞伎座の顔見世恒例の「櫓(やぐら)」が正面玄関の唐破風の上に揚げられました。櫓は、江戸時代に幕府公認の劇場である証でした。歌舞伎座の櫓はその伝統と誇りを受け継いだもので、大道具が製作し、鳶の方々が設置作業を行っています。

10月28日の午前中から作業は始まりました。まずは櫓の土台を作る作業からスタートです。

櫓の柱を屋根の上に運びます。

屋根の上で組み上げます。

櫓に幕をつけていきます。

完成です。
その17 道具帳
歌舞伎の大道具は「道具帳」と呼ばれる1枚の絵を基に製作されています。舞台を真正面から見たときの完成図のようなもので、1/50の縮尺で場面ごとに一枚ずつ描かれます。
写真は『寺子屋』の道具帳を描いているところです。
2014年10月公演、準備風景(その2)
10月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『鰯賣戀曳網』の2つ目の場面「五條東洞院の場」では、舞台の上のほうに紅葉が飾られます。その紅葉のボリュームを調整しているところです。

『鰯賣戀曳網』の五條東洞院の場のふすま絵です。高根宏浩先生の舞台美術で、大道具の絵描きが描いたものです。

『伊勢音頭恋寝刃』ののれんです。のれんも大道具が準備します。
その16 上敷(畳敷)その2
大道具では畳の部屋をあらわすときに「上敷(畳敷)」という長いゴザを用います。読み方は「じょうしき」です。今回は、転換の際の上敷の扱いについて、ミニレポートをしてみます。
以下の写真は、『伊勢音頭恋寝刃』の場面転換の練習風景です(2014年9月末の道具調べで撮影)。
廻り舞台(盆)を使って、裏側に飾ってある奥庭の場面にするのですが、上敷が邪魔にならないように盆の内側に寄せます。素早くきれいに寄せるのは、新人にとってはなかなか難しい様子。先輩が何度もお手本を見せて、指導していました!

左端が新人です。上敷をささっと寄せる練習中。

右の先輩がお手本をやってみせます。

新人ひとりで、何度も練習!
【大道具の道具】 上敷(畳敷)その1 はこちら
http://kabukizabutai.co.jp/saisin/odougunodougu/1578/
2014年10月公演、準備風景(その1)
10月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『伊勢音頭恋寝刃』奥庭。

『野崎村』。屋体の位置を確認しているところです。

ロープを結んでいるところ。結び方にもいろいろありまして、先輩(右側)が後輩に指導していました。大道具は天井にも吊り下げて収納しているのですが、このあたりもなかなか面白い世界です。
9月4日から歌舞伎座ギャラリー(歌舞伎座タワー5階)にて、「歌舞伎は旅する大使館<後期展示> 歌舞伎ファンを世界に」展がはじまりました。今回の展示では、1990年以降から最新の平成中村座ニューヨーク公演までの海外公演についてさまざまな切り口で紹介されています。
海外公演で上演回数の多かった『連獅子』『藤娘』などの衣裳やかつら、小道具の実物展示も。大道具のものとしては『連獅子』の「二畳台」が展示されています。お近くにお越しの機会がありましたら、ぜひおでかけくださいませ。

正面の舞台に展示されているのは『連獅子』の衣裳やかつら、小道具。衣裳の下にあるのが二畳台。ちなみに牡丹は小道具さんの扱いになります。
■■■ 歌舞伎座ギャラリー[歌舞伎は旅する大使館]■■■
■■■ <後期展示>歌舞伎ファンを世界に 概要 ■■■
【日程】
2014年9月4日(木)~2015年1月25日(日)
※10月24日(金)は14時開館
【休館日】
2014年12月27日(土)~2015年1月1日(木・祝)
【開館時間】
10:00~18:00
※最終入館は17:30まで
【会場】
歌舞伎座ギャラリー(GINZA KABUKIZA 歌舞伎座タワー5F)
【入場料(税込)】
一般:600円
小・中学生:500円(小学生未満無料)
団体:500円(20名様以上一律)
歌舞伎座ギャラリーについての詳しい情報やお問い合わせ先については以下をご覧下さい。
松竹株式会社 歌舞伎座ギャラリー
http://www.shochiku.co.jp/play/kabukiza/gallery/
2014年9月公演、準備風景(その2)
9月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『法界坊』「浄瑠璃 双面水照月」。白い布に包まれているものは浅葱幕。 舞踊のために所作台を敷いているので、雪駄を脱いでガチ袋に入れ、足袋で作業をしています。

『法界坊』「浄瑠璃 双面水照月」で浅葱幕(あさぎまく:手前の青い色の幕)を振り落とした直後。浅葱幕を仕込んだり、振り落としたり、落ちた幕をはけさせているのも大道具です。

上からのれんみたいにさがっている桜は「吊り桜(糸桜)」です。天井から降ろしてみると、想像以上に長いんですよ。 正面から見るとわかりづらいですが、手前とは別に奥のほうにも1列あります。
松竹大谷図書館は、演劇、映画に関する貴重な資料を収集、整理、保存し、研究に協力したり閲覧の場を提供している公益財団法人の図書館です。歌舞伎の資料も多く所有しており貴重な存在です。今月からインターネットを通じて寄付や協力を募るクラウドファンディングに参加し、所蔵約44万点の資料のうち、約5,000点を占める「芝居番付」のデジタル化実現を目指し支援者を募集されています。詳しい内容は以下の歌舞伎美人のニュースをご覧ください。
※10月29日にプロジェクトが成立されたそうです(募集は終了しました)。ご協力くださった皆様、ありがとうございました。
松竹大谷図書館の公式WEBサイト
http://www.shochiku.co.jp/shochiku-otani-toshokan/
【歌舞伎美人ニュース】
歌舞伎の芝居番付をデジタル化するプロジェクト、支援者募集
http://www.kabuki-bito.jp/news/2014/09/post_1196.html

2014年9月公演、準備風景(その1)
9月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『菊畑』の菊棚。

『御所五郎蔵』(廓内夜更けの場)。 屋根を浮かせて、ちょっと位置を調整をしているところです。屋体の中と外で声をかけあいながら、慎重に進めていました。

お客様に姿が見えるときは「たっつけ」を着用しています。写真の4人のうち3人がこれを着ていますね。背中と腰には歌舞伎座の座紋が入っています。
日本テレビの昼の番組「ヒルナンデス!」にて、秀山祭九月大歌舞伎に関する特集が2週にわたって放送されます。秀山祭の魅力をさまざまな角度から紹介されるようで、私たち大道具も取材に協力させていただきました。よろしければご覧いただけましたら幸いです。
ヒルナンデス! 毎週月曜〜金曜 11:55−13:55
http://www.ntv.co.jp/hirunan/
放送予定日:2014年9月8日(月)、9月15日(月・祝)
*都合により変更されることもあります。あらかじめご了承ください。
秀山祭九月大歌舞伎
平成26年9月1日(月)~25日(木)
http://www.kabuki-bito.jp/theaters/kabukiza/2014/09/post_79.html
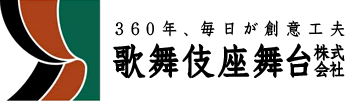
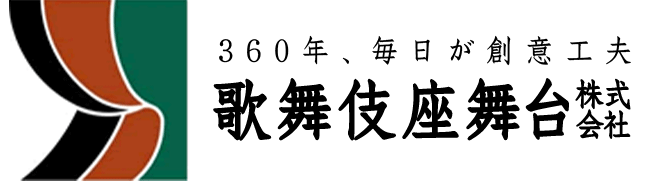
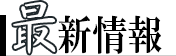
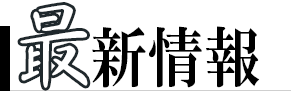
s-300x195.jpg)