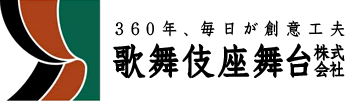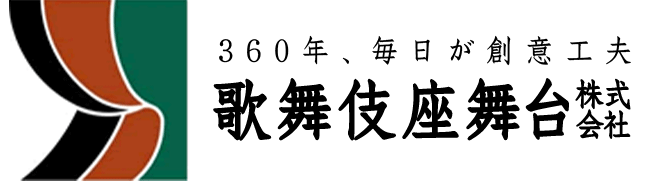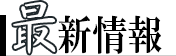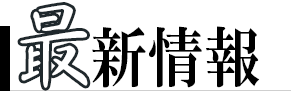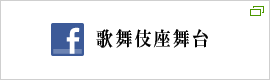2016年11月公演、準備風景(その2)
11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『御浜御殿綱豊卿』では、廻り舞台を使った転換があります。そのときに、上手(かみて)と下手(しもて)の端は、絵本をめくるようにして変化させます。これを「あおり」と言います。本番では、ささっとやってしまいますが、大道具が手で動かしています。

『御浜御殿綱豊卿』では、畳の大広間の場面があります。長いゴザのようなものを敷き詰めるのですが、きれいにとめておかないと、ゴザが動いてしまったりしますので、このあたりも神経をつかっております。
2016年11月公演、準備風景(その1)
11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『祝勢揃壽連獅子(せいぞろいことぶきれんじし)』の台を準備しているところです。親子四人で踊られる迫力ある舞台です。

『盛綱陣屋』の紅葉の立木です。葉は造花なのですが、それを枝に打ち付ける担当がおりまして、お芝居ごとに打っています。いろいろな状況を判断する必要があり、専門でないとできない仕事です。
2016年10月公演、口上の舞台
今月は、中村橋之助改め八代目中村芝翫 中村国生改め四代目中村橋之助 中村宗生改め三代目中村福之助 中村宜生改め四代目中村歌之助の襲名披露興行。口上(こうじょう)の舞台美術は、日本画家の朝倉隆文先生によるものです。朝倉先生の原画をもとに、弊社の絵描きが描かせていただきました。

第一美術課(絵描き)課長の山中隆成が、朝倉隆文先生の原画を元に、描いていきました。

実際に舞台に飾って、手直しを行う「道具調べ」の様子。

襲名を記念してくばられたTシャツを着て、舞台転換の仕事にとりかかります(初日の様子)。
歌舞伎美人ニュース
口上の舞台の写真(2点)も掲載されています。
http://www.kabuki-bito.jp/news/3597
2016年10月公演、準備風景(その1)
10月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『初帆上成駒宝船』。帆には、芝翫丈の定紋である祗園守(ぎおんまもり)が大きくかかげられています。

『藤娘』の造花を飾り付けているところです。房をつける位置を考えたり、花びらを整えたりと、みんな慎重に作業をしていました。
2016年9月公演、準備風景(その3)
9月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『碁盤忠信』の舞台転換の手順を確認しているところです。通常の演目ではやりませんが、新作や普段あまりやらない演目では、こうした時間を設けます。

『吉野川』の「かすみ幕」です。ひょこひょこと動く「かすみ幕」は、大道具が扱っています。ユニークな幕の使い方ですよね。
2016年9月公演、準備風景(その2)
9月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『元禄花見踊』の「吊り桜」を整えているところです。花のところがすぐにからまってしまいますので、目でチェックして手作業でほぐします。「吊り桜」は近くで見ると結構、長いんですよ。

『一條大蔵譚』「奥殿」の屋体です。左側の「花丸」は絵描き(第一美術課)、右の金色の文様は「奉書雲(ほうしょぐも)」と言う名称で塗方(第二美術課)が描いています。
2016年9月公演、準備風景(その1)
9月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『一條大蔵譚』檜垣の場面の門です。ちょっとだけ斜めにふって置いてあります。

『らくだ』の屋体を大工チーム(製作課)が調整しているところです。古そうな井戸もありますが、これも大道具です。
弊社の絵描き(第一美術課)の山中隆成が再興第101回院展に「記号」を出品し、入選いたしました。院展(正式名称は「日本美術院展覧会」)は、公益財団法人 日本美術院が主催運営している日本画の公募展覧会のことで、春と秋に開催されます。春は「春の院展」、秋は「再興院展」と呼ばれています。山中は、このたびの入選で再興院展に3回入選となりましたので「院友」(*)となりました。
山中の作品も展示される展覧会「再興第101回院展」が9月1日より東京都美術館にて開催されます。おでかけの際は、ぜひ山中の作品もご覧いただけましたら幸いです。
院展・日本美術院のホームページ
http://nihonbijutsuin.or.jp/index.html
再興第101回院展
日程:平成28年9月1日(木)~9月16日(金)
場所:東京都美術館(上野公園)

山中隆成(やまなか たかなり)
第一美術課 課長
昭和43(1968)年、神奈川県生まれ。多摩美術大学日本画専攻卒業。平成11(1999)年より歌舞伎座舞台で絵描きとして働き始め、翌年に正式入社。日本美術院特待(*)で歌舞伎座舞台の絵描きである後藤芳世の勧めにより、院展に出品をはじめる。2016年より院友(*)。大学時代の先生でもあり日本美術院同人(現・理事長)であった故・松尾敏男(まつお としお)画伯に師事。歌舞伎座が新開場した平成25(2013)年4月公演の最初の演目『壽祝歌舞伎華彩』、その一年後の平成26(2014)年4月の歌舞伎座公演の『壽春鳳凰祭』では、松尾敏男画伯が舞台美術を担当。師の描いた道具帳の意図を汲みとり、「囲い」(*)の図案を考えて描くなど、舞台の背景画を描く指揮をとる。平成18(2006)年の再興第91回院展をはじめ、過去に春の院展に3回、再興院展に2回、入選を果たしている。
*特待:再興日本美術院展覧会(院展)に20回入選、あるいは、奨励賞4回受賞、または日本美術院賞1回受賞で推挙される。
*院友:研究会員であることを前提に再興日本美術院展覧会(院展)に3回入選で推挙される。
*囲い:大臣囲いの略。舞台の上手と下手の黒御簾の前に飾る絵のこと。
第一美術課の仕事についてのインタビュー(山中隆成)
http://kabukizabutai.co.jp/daiichi_bijyutsu/
2016年3月「中村芝雀改め五代目中村雀右衛門襲名披露 三月大歌舞伎」の祝幕。美術は故・松尾敏男画伯、山中が中心となって幕を描いていきました。


2016年8月公演、準備風景(その2)
8月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。
2016年8月公演、準備風景(その1)
8月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『東海道中膝栗毛』。背景画を吊る作業をしているところです。

『嫗山姥』。左でのこぎりを持っているのは製作課、右でバケツを抱えて色の仕上げをしているのは塗方(ぬりかた)と呼ばれる第二美術課のメンバーです。製作課、第二美術課は普段は千葉県の松戸で仕事をしていますが、初日前には歌舞伎座に詰め、舞台で仕上げなどをやっています。