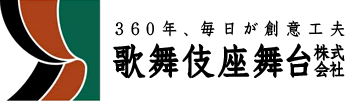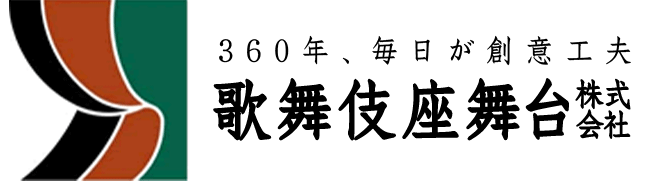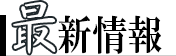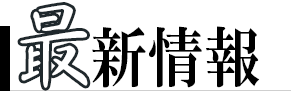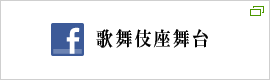2018年7月公演、準備風景(その1)
7月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『三國無雙瓢箪久(さんごくむそうひさごのめでたや) 出世太閤記』序幕の屋体(やたい)です。ちょっとユニークなデザインの城門です。

『源氏物語』では、桜が登場します。写真は仕込みの様子。造花担当者が丁寧に飾っていきます。
2018年6月公演、準備風景(その2)
6月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)』の舞台。大きな暖簾には、主人公の団七を演じる俳優さんの紋が描かれています。暖簾も大道具が担当します。

『三笠山御殿』の屋体(やたい)の中で、「二畳台」の準備をしているところです。
2018年6月公演、準備風景(その1)
6月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『野晒悟助(のざらしごすけ)』の舞台。ちょっと珍しい足場の道具です。

『巷談宵宮雨』の夜の場面。黒い布を用いて、舞台を作っていきます。
2018年5月公演、準備風景(その2)
5月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)』の山門。舞台機構のセリも使いながら、歌舞伎らしい間あいで転換させるよう心がけています。

『雷神不動北山櫻』の舞台。岩には、苔(こけ)が描かれています。
2018年5月公演、準備風景(その1)
5月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)』の大屋根の舞台です。集合して転換の手順を確認している様子。

『菊畑』の舞台。造花の菊の花を、大道具が整えているところです。そばで見ても、本物の菊のようなきれいな造花です。
2018年4月公演、準備風景(その2)
4月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『裏表先代萩』の舞台。歌舞伎では、部屋の奥の「大広間」がときどき登場します。これを「千畳(せんじょう)」と呼びます。不思議な遠近感ですよね。

歌舞伎では、ときどき広い畳の部屋があります。こうしたときには、ゴザを敷くのですが、ボーリングみたいに、どーんと投げて、一気に敷きます。かなり重いので、力とコツがいるんですよ(写真は『裏表先代萩』)。
2018年4月公演、準備風景(その1)
4月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『絵本合法衢(えほんがっぽうがつじ)』の舞台。場面転換の多い演目です。

『裏表先代萩(うらおもてせんだいはぎ)』の舞台。塗方(第二美術課)が、柱の部分を手直ししています。
ちなみにふすまの絵の部分は、絵描き(第一美術課)が担当。弊社では、こうしてそれぞれ専業で、技芸を追求しております。
2018年3月公演、準備風景(その1)
3月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『神田祭』の舞台。塗り方が手直しをしているところです。弊社では、自然風景や襖絵などの絵画的な部分を担当する「絵描き(第一美術課)」と、屋体の壁や塀などを担当する「塗り方(第二美術課)」がそれぞれ専業で仕事をしています。

『国性爺合戦(こくせんやかっせん)』の舞台。明国が舞台ということで、大道具もちょっと雰囲気が異なります。
2018年2月公演、準備風景(その1)
2月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『壽三代歌舞伎賑 木挽町芝居前』の提灯を飾っている様子。かなり大掛かりな転換もあり、迫力のある舞台です。

『熊谷陣屋』の屋体(やたい)。舞台に組み上げてから、塗り方が最終仕上げをしているところです。
2018年1月公演、準備風景(その2)
1月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前に行います。

『三人形』の舞台。板の部分は塗り方(第二美術課)、桜は絵描き(第一美術課)が担当します。

『車引』の牛車は、大道具の担当になります。歌舞伎らしい、シンプルなしかけが、場面をささやかに盛り立てます。