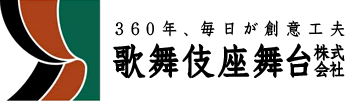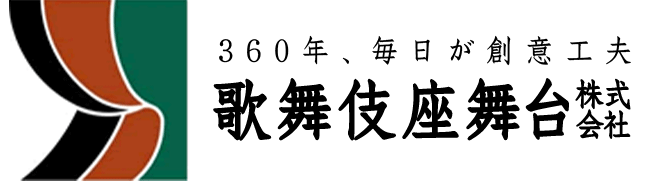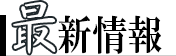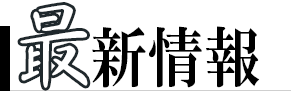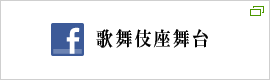2014年12月公演、準備風景(その1)
12月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『雷神不動北山櫻』の屋体。製作課が手直しをしつつ、塗方が色の仕上げをしているところです。

一番大きなセリを使って、大奈落から屋体を舞台にあげているところです。

『雷神不動北山櫻』二幕目「小野春道館の場」の屋体を彩る「花丸」。絵描きがひとつずつ手で描きました。その数は、60を超えます。
2014年11月公演、準備風景(その2)
11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『熊谷陣屋』の「幔幕(まんまく)」をはっているところです。転換チームのなかに、のれんや幔幕などの布を扱う担当者がいます。

『井伊大老』の背景画の手直しをしているところです。

『鈴ヶ森』。 水をあらわした道具が置かれていますが、これも大道具が作ります。この「水」は、ラストでお話を展開させる役目も担っています。
2014年11月公演、準備風景(その1)
11月歌舞伎座公演の「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『熊谷陣屋』の門の位置を確かめているところです。この門は「陣門」と呼んでいます(『盛綱陣屋』にも登場します)。

『熊谷陣屋』の所作台を敷いているところです。

『御存鈴ヶ森』の石塔をセットしているところです。慎重に位置をはかっていますね。
2014年10月公演、準備風景(その2)
10月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『鰯賣戀曳網』の2つ目の場面「五條東洞院の場」では、舞台の上のほうに紅葉が飾られます。その紅葉のボリュームを調整しているところです。

『鰯賣戀曳網』の五條東洞院の場のふすま絵です。高根宏浩先生の舞台美術で、大道具の絵描きが描いたものです。

『伊勢音頭恋寝刃』ののれんです。のれんも大道具が準備します。
2014年10月公演、準備風景(その1)
10月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『伊勢音頭恋寝刃』奥庭。

『野崎村』。屋体の位置を確認しているところです。

ロープを結んでいるところ。結び方にもいろいろありまして、先輩(右側)が後輩に指導していました。大道具は天井にも吊り下げて収納しているのですが、このあたりもなかなか面白い世界です。
2014年9月公演、準備風景(その2)
9月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『法界坊』「浄瑠璃 双面水照月」。白い布に包まれているものは浅葱幕。 舞踊のために所作台を敷いているので、雪駄を脱いでガチ袋に入れ、足袋で作業をしています。

『法界坊』「浄瑠璃 双面水照月」で浅葱幕(あさぎまく:手前の青い色の幕)を振り落とした直後。浅葱幕を仕込んだり、振り落としたり、落ちた幕をはけさせているのも大道具です。

上からのれんみたいにさがっている桜は「吊り桜(糸桜)」です。天井から降ろしてみると、想像以上に長いんですよ。 正面から見るとわかりづらいですが、手前とは別に奥のほうにも1列あります。
2014年9月公演、準備風景(その1)
9月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『菊畑』の菊棚。

『御所五郎蔵』(廓内夜更けの場)。 屋根を浮かせて、ちょっと位置を調整をしているところです。屋体の中と外で声をかけあいながら、慎重に進めていました。

お客様に姿が見えるときは「たっつけ」を着用しています。写真の4人のうち3人がこれを着ていますね。背中と腰には歌舞伎座の座紋が入っています。
2014年8月公演、準備風景(その3)
8月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『怪談乳房榎』の序幕「隅田堤の場」。小さな小屋は出茶屋。葭簀(よしず)が立てかけられています。背景の絵は浅草の隅田川の風景。待乳山(まつちやま)のふもと(下手側)には芝居小屋が描かれており、中村屋の定紋である角切銀杏(すみきりいちょう)の櫓(やぐら)があがっています(この写真には、写っていません。すみません!)。

『怪談乳房榎』の薮(やぶ)を作っているところです。大道具では「薮を打つ」という言い方をします。今月は薮はそれほど多くありませんが、たくさん出るときは薮を打つ作業も結構時間がかかります。薮は生きた植物を使うので、近くを通ると笹団子のようなふわっとした香りがします。
2014年8月公演、準備風景(その2)
8月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『たぬき』に登場する棺桶(早桶)と薪です。薪のほとんどは大道具が作りますが、役者さんが手に持つ薪は、小道具さんが作られます。 小道具さんにうかがってみると「(大道具と)打ち合わせなくても、だいたい同じ感じの色味になるんだよね〜」と言われていました。阿吽の呼吸。

このなまこ壁は『たぬき』の芝居茶屋の二階の場面(二幕目の第一場)で使われるものです。 客席のお客さまからは、茶屋の座敷の窓から少し見える程度だと思いますが、実際はこんなに大きな壁なんですよ。
歌舞伎美人のニュースにこのなまこ塀が写った舞台写真が掲載されていましたので、以下にお知らせします。見比べてみると楽しいかもしれません。
http://www.kabuki-bito.jp/news/2014/08/_8.html
2014年8月公演、準備風景(その1)
8月歌舞伎座公演の製作準備や「道具調べ」の様子をご紹介します。「道具調べ」とは、本番通りに道具を飾ってきちんとできているかを確認したり、手直しをしたりするもので、初日の数日前などに行います。

『恐怖時代』の「殿中酒宴の場」。塗り方が仕上げの筆を入れています。

『恐怖時代』「殿中酒宴の場」のパーツ。これはまだ製作途中で、このあと黒いふちと引き手をつけて、ふすまの形となります(下手の黒御簾の前につけます)。

舞台課のメンバーが『龍虎』の岩の手直しをしています。