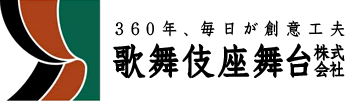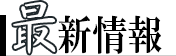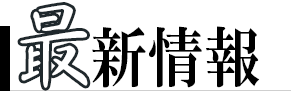歌舞伎座の大道具を支える職人 造花 その2
歌舞伎の造花について深く知るための連載記事の2回目です。その1をご覧になっていない方は、こちらもご覧ください。
(取材・文 田村民子)

(左)酒井造花製作所(花善)の玄関。(中)お仕事場には色とりどりの造花がたくさん。手がける造花の種類は100種類をゆうに超えるという。(右)花善社長の酒井克昌さん。
酒井造花製作所、通称・花善(はなぜん)は、東京都北区の静かな住宅街のなかにあります。ドアを開けるとすぐにお仕事場になっており、色とりどりの造花がところ狭しと並んでいます。部屋全体がふわっと明るい雰囲気で、思わず心が浮き立ちます。さっそく社長の酒井克昌さんにどのような手順で造花を作られているのか、うかがってみました。
酒井さんによると、作り方には主に2パターンあるそうです。1つ目は、白い紙をクッキーの抜き型のようなもので抜いてから染めて色を付ける方法。たとえば藤の花のように1枚の花びらのなかで白と紫で色のグラデーションをつける場合などは、こちらのやり方にします。2つ目は、色をつける順序が逆で、まず刷毛などで紙の両面に色をつけてから、型で抜くというやり方です。ものによって狙う色のトーンが細かく異なるため酒井さんが慎重に色味を検討しています。

(左)型を抜く機械。(中)抜き型。銀杏、桜、紅葉、葉などの他、たくさんの種類の抜き型があった。手に持つとずっしりと重い。(右)菊の葉の抜き型。葉の大きさは2種類ある。

(左)色を染める作業場。(右)染め上がった桜の造花。手仕事ならではの微妙な表情がある。
造花のひとつひとつを間近で見ると、実物よりもうんと大きかったり、花びらの形も随分異なったりしていることに気付きます。でも、不思議なものでパッと見ると、どの花かすぐにわかります。酒井さん曰く、「歌舞伎の造花は、それらしく見えること、芝居の雰囲気に合っていることが大事」。それを具体的な形に落とし込んでいるのが酒井さんのお仕事なのですが、話をうかがってみると想像以上に細かく作り分けていることがわかります。
たとえば花びらや葉の素材は、演目や場面に応じて模造紙や半紙、薄い和紙、布など繊細に使い分けています。舞台用の造花は近くで見るものではないので、素材の質感にそれほどこだわらなくてもよいのではないか…と素人は考えてしまいますが、やはり人間の眼は知らず知らずのうちにディティールの差を見分けてしまうもの。質感へのこだわりが、造花の質をあげているのです。

(左)古典歌舞伎などで使われる桜。これは大道具に納品された状態のままの束。枝は本物の桜なので、1本1本に個性がある。(右)『ぢいさんばあさん』などの新歌舞伎では古典歌舞伎よりも写実に近い造花が使われる。
お話をうかがっていて興味深かったのは、枝へのこだわりです。たとえば桜の花には、本物の桜の枝を植木屋から仕入れて用います。枝はソメイヨシノではなくヤマザクラのほうが、色などがふさわしいとのこと。また、しだれ桜にするための造花では、本物の柳の枝を使うそうです。(しだれ桜は『喜撰』などに登場します)。だれもが知っている桜などの植物は、少しでも違和感があるとニセモノ感が漂ってしまいます。歌舞伎の花々は写実でもなく、虚飾でもない、本物を超越した魅力があります。その秘密の一端を垣間見たような気がしました。
*次回は、『藤娘』の藤の花などについてお伝えします。お楽しみに!